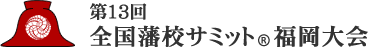次代を拓いた国際人 金子 堅太郎
セオドア・ルーズベルト─運命の邂逅
海外調査旅行の最終寄港地は再びアメリカであった。数ヵ月前、渡航準備を進めていた際、ビゲローが紹介状を持参して堅太郎を訪問してきた。ビゲローはかつて東京大学予備門の講師をしていた時にフェノロサから紹介された友人でありハーバード大学の同窓でもあった。
「今度、欧米に行くそうだが、是非とも紹介したい男がいる。私の親友だが、君にとっても得難い友人になってくれるものと思う。この男は必ず将来大統領になる。会っておいて損はない」
その勧めによってルーズベルトに会うための米国再訪である。ルーズベルトは堅太郎より五才下で当時、三十二才。行政改革委員長を務めており精力的に活動していた少壮の政治家である。第一印象から相通ずるものがあり、帰国までのわずかな期間にも何度もお互いの宿舎を行き来しては歓談に時間を忘れた。この出会いこそが日本の運命を左右する邂逅であり、ターニングポイントとなったのである。
明治二十三年(1890年)六月六日、約一ヵ年の長期海外視察旅行を終えて横浜港に帰着。家族との再会の喜びに浸る暇もなく、視察報告書や議院建築の意見書の執筆・出版に明け暮れ、その年の九月、日本法律学校の初代校長に就任する。旅行中に内報は受けていたが、固辞するつもりでいた堅太郎は、帰国報告を兼ねた辞退申し出の際、山県有朋を訪ねて再度要請されてしまう。
「すまんが、もう決めたことなのだ」
「私は今まで学校の校長になった経験もないばかりか、その器にありません」
「いや、山田(顕義司法大臣)も君を措いて外にないと言っておる。我輩もである」
「我が国にとって法がどれほど重要であるかは、君が一番良く知っておる。日本の法を学ぶ先鞭をつけて欲しいのだ」
明治二十三年(1890年)九月二十一日、日本法律学校(日本大学の前身)は堅太郎を初代校長に迎えて開校されたのであった。堅太郎は開校式に臨み、告辞を述べた。
「和魂を以って学問の基本となし、漢才と洋才とによってこれを実施・応用せば、実に完全の学問と謂おうべき。ねがわくば、日本法律学校はこの主義を以って本邦の法令を講究せられんことを願う」
藩校・修猷館で徹底して学んだ和魂があったからこそ、英学への希求の念が育まれ、時代を拓く知識が培養された。それは堅太郎自らが実践し続けてきた志しある道だったのである。堅太郎はこの校長就任以前にも専修大学創立、慶応義塾偉大学法学部開設にも尽力している。
明治二十四年(1891年)九月九日、堅太郎は国際公法会の準会員に選ばれたとの通報を受け取る。ハンブルグ大会で開催された同会会議上で選出されたのである。アジア人として初めてのことであった。国際公法会とは国際間の諸問題を解決・仲裁し、諸外国の平和的な交流を維持することを目的に組織された学術団体である。国際公法会ではすでに設立の翌年、明治八年(1874年)に米国会員である・デヴィッド・フィールド氏から「条約改正」の問題提起があったが、日本の国情や法律についての情報も知識も行き渡っていなかったため、沙汰止みになっていたという経緯があった。海外視察の際にオックスフォード大学のホランド教授からアドバイスを得ていたが、欧米諸国の法学関係有識者は堅太郎の存在を知るに至り、推挙したのだろう。広報官としての活動が功を奏したのである。ホランド教授からも丁寧な書簡が届く。翌年の明治二十五年(1892年)スイスのジュネーブで開催予定の国際公法会総会に出席し、治外法権撤廃の問題に関する日本の考え方を積極的に表明し、日本の法典や欧米諸国との間に締結した諸条約を国際公法会に提出するよう勧めてきたのである。
堅太郎は早速、国際公法会総会への出席許可を得るべく、松方正義首相、榎本武明外相、田中光顕法相のほか伊藤博文枢密院議長や井上馨に内申する。いずれも条約改正を達成する好機として諸手を挙げての賛成となった。堅太郎は暑中休暇を兼ねて国際公法会総会出席を願い出ている。アメリカ・ボストンで旧知の政治家・学者からも意見を聴き、英国においても学士や政治家との意見交換を行なうため各地を経由することにしたのである。
堅太郎は出発前に挨拶のため伊藤博文の別荘を訪ねた。幕末から現在に至るまで、伊藤は条約改正を宿願としており、その情熱を誰よりも認識していたからである。
明治二十五年(1892年)六月二十七日、横浜港を出帆。まずはアメリカ・ボストンをめざした。
ボストンではハーバード大学時代の旧師ホームズ大審院判事に接見する。ホームズ判事は、これからの外交、政治に経済の問題は欠かせないと語り、自らの蔵書を堅太郎に贈与するのであった。堅太郎は師の意図するところをすぐに理解した。諸外国に対する力は、法の改正やそのアピールだけでは不十分である。列強と肩を並べるだけの経済力を持つことではじめて対等の交渉が可能となる。あるいは経済発展の可能性を示す必要がある。堅太郎の目は次の目標を模索し始めるのである。ホームズ師が放った言葉が重きを成していた。
「条約改正すなわち諸外国との交渉の下地は最後に腕力がモノを言う」
腕力とはいうまでもなく軍事力である。腕力を支えるのはとりもなおさず経済である。海外視察で目にしてきた数々の事物がその発言を裏付けした。パリ万国博覧会で遭遇した鉄塔建築、ロシアのバルチック造船技術だけではない。堅太郎は製鉄を中心とする重工業の発展が国力増強に欠かせないことを想起していた。
明治二十五年(1892年)九月五日、スイス・ジュネーブの市会議事堂で国際公法会総会が開幕した。参加者は堅太郎を含め三十九名。各国の著名な大学教授、裁判官、弁護士、外交官等が集っている。ホランド教授の姿も見える。会議上での堅太郎のスピーチは各国列席者の心を見事にとらえるのであった。閉会後、会員の一人ハインベルゲル氏が言った。
「先日の貴下の演説を聞いた会員で日本の条約改正に異議を唱える者は一人としていないであろう。おそらく内々に通達があるはずである。日本政府の要求する条約改正に反対する道理がない。ただ種々の理屈をつけて反対する声があがるとすれば、それは日本の急速な発展がある。中国貿易の利権を狙う欧米諸国は日本にその利益を奪われることを恐れている。この反対を打破するには、言論ではない。兵力だ。兵力あるのみ」
会議出席前に聞いたホームズ判事の発言が現実味を帯びてきた。堅太郎は日本の近未来の予想図を描くことをためらった。そこには軍事の必要性が潜んでいたからである。
明治二十七年(1894年)七月十六日、治外法権撤廃を初めて認めた日英通商航海条約がロンドンで調印された。日清戦争が勃発するわずか十日前のことであった。