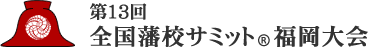寄稿
宮本 雄二
(宮本アジア研究所代表・元駐中国特命全権大使)
修猷館高等学校・昭和40年卒業
明治維新は、実質的な革命、それも相当の革命だった。それをあの程度の犠牲でやり遂げたのは、やはり見事というしかない。幕末から維新の激動に触発されて、日本各地で人材を輩出した。黒田藩の筑前では、明治の初めにアメリカ留学をした金子堅太郎、団琢磨、そして栗野慎一郎が、それに当たる。栗野(1851年生まれ)は外務省に入り、条約改正などに力を振るった後、最後は駐仏大使をつとめた。同じ筑前の山座円次郎(1866年生まれ)は、政務局長として小村寿太郎外務大臣を支え、日露戦争後の幕引きに奔走し、ポーツマス条約の締結に尽力する。1914年、駐中国公使(中国には大使ではなく公使が派遣されていた)のときに将来を惜しまれながら北京で客死した。そして広田弘毅(1878年生まれ)である。山座に強く勧められ、外務省に入り、外務大臣から、最後は総理大臣をつとめた。
多くの修猷館卒業生が外務省に奉職した。福岡は、博多商人に代表されるように、外に開かれた都市であった。そして江戸時代は、常に開港都市長崎を意識していた。このような外部世界に対する強い関心が、自由独立の気風を生み、修猷館の卒業生たちを対外関係に押しやったのであろう。
清田 瞭
(㈱日本取引所グループ代表執行役グループCEO)
修猷館高等学校・昭和39年卒業
昭和39年に修猷館を卒業して今年で51年になる。東京オリンピックの年に東京に出て1年間の浪人生活ののち早稲田大学に入学した。当時の日本はまだまだ発展途上国で新幹線や首都高速道路をオリンピックに合わせて突貫工事で完成させたばかりであった。東京オリンピックの組織委員会会長の安川第五郎さんが修猷館の先輩であることは、お会いしたこともないのに妙に誇らしく感じたものである。それから半世紀、5年後の2020年に再び東京でオリンピックが開催される運びとなり運が良ければ2度目のオリンピックを観戦出来る事になりそうである。さて、東京証券取引所を傘下に抱える日本取引所グループのCEOとして現在取り組んでいる上場企業の「コーポレートガバナンス強化と企業の稼ぐ力の向上によるROE(株主資本利益率)を意識した経営」はようやく緒についてきた所であるがアベノミクスのおかげもあって株式市場は活況を続けている。今年は東証への新規上場も活発で、久しぶりに100社を超えることが期待されている。企業の新陳代謝の活発化は経済成長の原点であり、戦後すぐのソニー、松下、トヨタ、など、多くの新興企業が超巨大企業へと成長した。またバブル崩壊後もソフトバンク、ファーストリテイリング、KDDI、楽天、ヤフー、ニトリ、日本電産、などが新規上場し、その後急成長したことは記憶に新しい。イノベーションを引き起こす新興企業の登場と成長分野への投資こそが次世代の日本を作って行く原動力である。我が福岡からも多くの新規上場企業が現れて欲しいと願っている。
川崎 隆生
(西日本新聞社社長)
修猷館高等学校・昭和44年卒業
修猷館は、足掛け4世紀の時を経て「修猷山脈」と称される人材の連なりを築いた。地底から湧き上がるエネルギーが山脈を形成するように、修猷山脈も先人の熱き志が造山活動の源にある。文化・ジャーナリズム部門4氏の生きざまもマグマのように熱い。
福本日南が創刊した新聞「日本」の後輩に、あの正岡子規がいる。ロンドンで出会った無名の博物学者南方熊楠の才能を見抜く眼力と、日本人の精神構造に忠臣蔵の思想を組み込んだ文章力が今も語り継がれる。那珂郡春吉村生まれの寺尾寿は、早良郡鳥飼村出身で2歳上の金子堅太郎と知と才を競った。天文学を学びながら試験直前、友を誘って芝居や落語を楽しむ粋人でもあった。
夢野久作の異才ぶりは、奇書「ドグラ・マグラ」が証明する。一方、九州日報の記者として記した関東大震災の現地報告は、朝鮮人の暴動説など誤った風評と闘い、真実を追求している。和田三造には東京美術学校時代、八丈島に向かう航海で漂流、伊豆大島にたどり着いたという伝説が残る。
彼らをはじめ多くの文化人、ジャーナリストが継承してきた「修猷文化」の最大の特徴は多様性だ。画一的であることを何より嫌い、自分の世界に閉じこもることはない。異質なものと出会ってたじろがず、その本質を理解しようとする。そのうえで自らを見つめ、個性を磨く。原点はすべて10代の一時期、修猷館で学んだことにある、と思う。
津田 純嗣
(株式会社安川電機代表取締役会長兼社長)
修猷館高等学校・昭和44年卒業
2014年修猷館がラグビー全国チャンピオンの東福岡高校を破り県大会優勝の快挙を上げた時には、メディアでは文武両道の修猷館ともてはやし、私自身も大いに喜んだ。ラグビー部員が猛練習の後、皆で塾へ行って勉強する姿をテレビ放送で見て、若者の「今」に打ち込む賢明さに感動もした。
藩校であった修猷館における文武両道の意味は「文」は「教養」であり、「武」は「武士の精神」と読み替えてよいだろう。「武」は新渡戸稲造がその著書「武士道」で語る「高い身分に伴う義務・規律」への忠誠心と気概であり、スポーツマンシップに繋がるものでもある。藩校修猷館に通う武士の子弟は皆が幼少期から、それを教えられ、修猷館の中では当たり前の文化であったと想像される。その文化のもとでは「教養」は行動するための「知恵」を得ることを明確な目的とした知識の習得であったはずである。
武士道の精神は西洋の騎士道でのNoblesse obligeと共鳴するものがあり、それ故に維新から明治にかけて留学した若者達は欧米の文化に臆することなは無かったと聞く。誇りを持って学び、「知恵」を持ち帰り、明治以降の時代を築いた。
私が勤務する安川電機の創業者であり、1964年の東京オリンピックの組織委員会会長を務めた安川第五郎先輩も米国ペンシルバニア大学に学び、帰国後、今からちょうど百年前の1915年に若干29歳で会社を興した。時はまさに、第二次産業革命期で工場の動力が蒸気機関からモーターに変わろうとしていた。「技術立社」を標榜し日本の技術で西洋に立ち向かおうとの高い志であった。事業には苦しみ、17年間の赤字経営となるが、そんな中でも、日本に技術者を育てることは自らの責務であると、その父安川敬一郎先輩が「技術に堪能なる士君子」養成のために創設した明治専門学校(現在の九州工業大学)の教壇に毎週、立ったという。