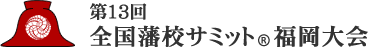次代を拓いた国際人 金子 堅太郎
英学への思い断ち難く志を貫く
翌明治三年(1870年)十月、藩命によって東京遊学が命じられた。昌平校に入学するのである。各藩から優秀な人材が集まっていたが、堅太郎ほどの逸材は存在せず、教授に堂々と意見を述べる学生もまた居なかった。勇躍して上京したが、翌明治四年(1871年)、廃藩置県が発布され藩費留学生は一時帰省せよという。藩から学費が支給されなければ勉学はたちゆかない。だが、このまま福岡に帰っても将来の見込みはないように思われた。何よりも学は道半ばどころか入り口にさえ到達していない。堅太郎の頭にあったのは英学の修得である。修猷館の西寮・南寮・時計の間・北寮で、論語・孟子・大学・中庸、小学・史記、十八誌略・左伝、書経・詩経・近思録・資治通鑑・通鑑項目はすでに修得している。漢学を学び謡曲まで習っている。時代の趨勢を見ても諸外国と対等にわたりあうだけの語学と知識を身につけなければならない。
『有志在途』
志しあれば道あり。堅太郎は在京の旧筑前藩士で司法省の判事・平山能忍の学僕になる道を選ぶ。平山は勤皇の志士として知られた平野國臣の弟で、のちの修猷館の英語教師・平山虎雄の父である。平山は堅太郎の英学への篤い志を知り、さらに平賀義質を紹介した。同藩の出身判事で米国帰りである。平賀もチンチク壁の無足組という軽輩の出ではあったが、漢学・蘭学を修め、長崎の海軍伝習所にも藩の留学生として入所している。第一回の福岡藩海外留学生にも選ばれた俊才であった。帰福後、藩内の子弟に英語を教えていた。その頃の少年の一人に当時、神谷駒吉(養子で他家を継ぐ)と呼ばれていた団琢磨がいる。
ちなみに平賀は栗野慎一郎の師でもある。平賀が司法省判事に任命されて間もない頃、堅太郎は学僕として平賀家に入る。御用箱を持って司法省に供をするのだが、誰よりもよく働き、熱心に英語を学ぶので平賀も特に目をかけた。司法省の待合室での待ち時間にも英語の本を開いている。すでに団家に養子に入っていた琢磨もその後、同部屋となり英語の勉強を一緒にするようになっていた。琢磨は堅太郎より五才年少であったが、気が合ったのか兄弟のような仲となっていくのに時間はかからなかった。実際、その後、妹の芳子が琢磨と結婚して義弟になったほどである。
同年十月のことである。平賀は司法省の門を出るなり堅太郎に言った。
「君に供をさせるのは今日限りなり。長々ご苦労であった」
「えっ…?」
まだ四ヵ月しか経っていない。落胆する堅太郎に平賀の返答は予想を超えるものだった。
「今度、岩倉公一行の欧米巡回とともに旧藩主長知公も自費を以て米国に留学せらるるにより、君にその随行を命ぜられるつもりなり。また予は岩倉公の一行とともに洋行を命ぜられたり。ついては本日、予とともに黒田邸に至り老公(長薄公)よりお沙汰あるなり」
堅太郎はあまりの歓喜と驚愕で胸がふさがり、しばし口を聞けない。その後、平賀に随って赤坂溜池の老公の寓居に赴いた堅太郎に、長薄は慈愛に満ちた言葉を下す。
「今度長知が留学するにつき、金子にも同行せしめんと欲す。封建時代のごとく側近を随行しては修学のためにならず。ゆえに政府に差し出す願書にも随行ではなく同行とするつもりなり。ついては君臣の関係を離れ、まったく長知と同行する学生と心得ゆべし。また幾年かかりても学資は当家より支弁すべければ、必ず一科の専門学を卒業して帰国のこと」
堅太郎は感涙が両眼に溢れ出てくるばかりで感謝の言葉も出せず、ただただ平身低頭して謝意を表すよりほかなく、熱い涙が己が手の甲に垂れるのだった。傍にいた平賀も頭を下げる堅太郎に言った。
「近々出発となる。洋行の用意をなすべし」
平賀邸に帰り夫人や同僕に報告する。皆が歓声を挙げて喜び祝福してくれたのが、何よりもまた嬉しく眼はまたも潤むのであった。
黒田長知は米国留学願書を政府に提出し文部省の許可を得ると宮内省に同行させた。階下で土器に神酒が注がれ拝受する。堅太郎は感激を一刻も早く郷里の母に伝え、父と祖母の墓前に報告したいと思うが、汽船の便宜がかなわず帰郷を断念せざるを得ない。母・安子には長い手紙を書く。父の形見であった刀・永正祐定と廃刀令発布の時に断髪した一包の髪、宮内省で拝受した土器も同封した。
「もし天運つたなく彼の地で死去した場合は、この髪を父の墓の隣に埋葬して欲しい」
堅太郎は十八才になっていた。
洋行の準備は着々と進んだ。長薄は堅太郎に横浜の英国人仕立屋で洋装の手はずまで整えてくれたのであった。さらに、西洋料理の送別会を開いてくれた。かつて蘭癖大名とまで呼ばれた長薄と平賀は楽しげに喫するが、長知も堅太郎も琢磨も西洋料理を見るのも初めてでバターの臭いで口数もない。ローストの牛肉から血が出るのを見ると食欲よりも嘔吐寸前の体で青ざめる三人であった。
「横浜出帆後は日本食はない。すべて西洋料理のみ。試食せよ」
長薄は命じるが、ほとんど手付かず状態である。
「洋行せんとする者とは思えぬ」
平賀は大笑いするのであった。
明治四年(1871年)十一月十二日、汽船アメリカ号は横浜を出発する。携行書は英和辞典と日用単語編のみ。唯一歴代天皇と和漢年表を記したものが日本字の書である。もし論語や孟子、歴史、詩文などを持っていけば米国留学中の英語習得の妨げになると考えたからである。
洋上で思わず望郷の漢詩を口ずさむ日があり、夕陽に涙滲む日を重ね、鼠に足の親指を齧られつつの洋行には山川捨松、津田梅子、永井繁子、吉益亮、上田悌ら日本最初の女子留学生も同船していた。後に堅太郎を大抜擢し、日本近代化に貢献させる仕事へと導いた使節団副使の伊藤博文も同行の一人であった。
十二月六日、号砲で華々しく迎えられアメリカ・サンフランシスコに入港。グランドホテルで盛大な歓迎会が催された。後に語り草となった英語による伊藤博文の「日の丸演説」は、この時の聴衆に向かって行なわれたものである。
米国での留学先はボストンであった。すでに留学していた井上良一、本間英一郎に迎えられる。堅太郎はまず小中級学校に通って英語の基礎を学ぶことにする。琢磨とともにアップルトン街に下宿し、ライス・グラマー・スクールの第4級生に入学し八才から十三才の子どもに混じっての授業である。「はじめは鉛筆を削ってばかり」の堅太郎だったが、次第に修得を早め、明治七年(1874年)四月、卒業時には卒業生代表として告別演説をするまでになった。
ライス・グラマー・スクール普通学校に入学して一年ほど経った明治六年(1873年)夏、一つの出会いがあった。アリソン教師一家に誘われて避暑地に訪れたリゾート・ホテルでのことである。マサチューセッツ州スプリングフィールドに住むアベイ氏からキャリイ嬢を紹介されるのである。ダンスをはじめて目の当たりにした堅太郎が、宿泊客から勧められダンスを楽しんだ相手がキャリイ嬢であった。二週間の滞在中、毎晩のようにダンス『メリーウイドー・ワルツ』を踊る二人であった。勉学一辺倒だった堅太郎も二十一才である。淡い恋が芽生えたとしても不思議はない。ボストンに帰る前日、堅太郎は母・安子から貰った博多織の紙入れをキャリイ嬢に渡す。
「二週間、貴女のおかげで本当に楽しく過ごせました。有り難う」
貧しい留学生だった堅太郎にはそれが精一杯であった。