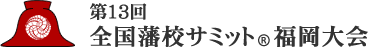次代を拓いた国際人 金子 堅太郎
ふたたびの東京での日々
明治十一年(1878年)九月二十一日、二十日間にわたる太平洋横断の航海を終え、横浜港に帰港した。團琢磨とともにすぐさま列車で東京に向かう。一刻も早く黒田家に帰国の挨拶をしなければならない。はやる気持ちを抑えつつ長薄に面会を乞う。
郷里・福岡に赴いたのは帰国挨拶もひととおり終わった十月半ばのことである。久し振りに対面する母や弟妹たちと語り尽くせぬ時を持つ。親戚や近隣の住人たち、かつての学友たちも押し寄せた。だが、畏敬の眼差しがやがて奇異なものを見るように変化していくのを感じ始める。サムライでありながらアメリカ人的気質をまとった堅太郎は、自分の身の置き場のないことに気づくのである。八年間という年月は堅太郎ばかりか、故郷を変えるに十分であった。目まぐるしい時代と人心の変化に逆に取り残されたような思いを抱くに至る。事実、ボストン留学時代、何かと親身に世話をしてくれた井上良一はハーバード大学卒業後、東京大学教授にまでなったが、精神的ショックから自殺してしまう。堅太郎を支えていたのは、米国の友人たちとの書簡による交流と黒田家への報恩のみであった。国に尽くす仕事を得ること、この目的のために我を失うことはできなかった。堅太郎と名を変えたのはこの時である。
※文中は混乱を避けるため堅太郎としている。志操堅固の意なのか、徳の字を堅と改めている。
ふたたび上京したものの希望する職の当てがあったわけではない。官僚となって中央政府で活躍するという旧主長薄・長知の意に応えたいと思うが、藩閥色の色濃い明治前期、福岡藩の堅太郎にはなかなか機会はめぐってこない。何とか福岡県令・渡辺清の紹介状を持って司法卿、司法大輔・山田顕義に面談かなうが、判任御用掛月俸二十五円の処遇である。到底納得できるものではない。当時の東京大学法学部卒業生の月俸が二十五円であった。何のために八年もの長い間、黒田の私費を投じて貰い米国の知識を学んだのかわからないではないか。どんなに貧しくても、地位が低くても誇りを失わない堅太郎は、金額の多寡よりも労苦の価値を判断されないことへの憤りがあった。
結局、堅太郎が就いたのは東京大学予備門の英語講師の職である。英語以外にも歴史を講義する。哲学教授であった米国人アーネスト・フェノロサに知遇を得たのは、この講師時代である。美術研究家でもあったフェノロサは後にボストン美術館の充実に貢献している。フェノロサを通じてビゲローを知り、ビゲローからセオドア・ルーズベルトへの紹介状を貰うことになるわけで、まさに運命に導かれた出会いの妙であった。
明治十二年(1879年)八月には、英語、歴史以外に文学も教授するようになる。授業以外の時間は法律と哲学の勉強に当て、なおかつ英国法の入門書の発刊にも携わるようになった。英米法に関する論文を書く、憲法私案を発表するなど着実に留学の成果を披瀝する機会を持った。
やがて学識の高さと弁舌さわやかな堅太郎は耳目を集める。明治十三年(1880年)一月、元老院大書記官の推薦で元老院に月俸百円で採用される。官僚へのスタートを切ったのであった。二十八才の時である。同年四月には、権少書記官に任ぜられ、条約改正や帝国議会開設の建白書や請願を管理する立場になった。
さらには西欧保守派のエドマンド・バーク野学説を紹介し注目されたため、十二月、明治天皇の侍講・元田永俘を通じて天覧するという機を持つに至るのである。