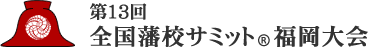次代を拓いた国際人 金子 堅太郎
伊藤博文との再会─憲法起草へ
明治十三年(1880年)、堅太郎は青森県令山田秀典の次女・弥壽子と結婚。弥壽子はまだ十六才の乙女であった。胸の内にあった初恋の人・キャリイ嬢の面影を封印し、自分の職責を全うできる結婚を選んだのである。堅太郎は次第に法の専門家として多忙を極め、政治論略を上梓するなど独自の解釈が反響を呼んだ。日本の近代化のためには憲法制定が急務である。参議・伊藤博文は痛切にその必要性を感じ、勅書を賜る。明治憲法すなわち大日本帝国憲法起草の青写真が徐々にかたちを現しはじめたのである。
明治十七年(1884年)四月、元老院の権大書記官に昇進。伊藤博文はエドマンド・バークの政治理論を機軸に明治日本に相応しい国体理論を論じる堅太郎に着目する。
「元老院にもかくのごとき憲法学者がいるのか。一体何者だ」
「おそらく金子書記官に相違ないでありましょう」
随行の三好退蔵は伊藤博文に進言する。学識・経験・性行すべてにおいて堅太郎以外にはいない。伊藤博文は確信したのであった。その後ほどなくして堅太郎は憲法起草の一員に加えられる。当時伊藤の秘書官を務めていた井上毅の案内で伊藤博文と面談する。
「君に来て貰ったのはほかでもない。我輩の秘書官になってくれぬか」
唐突な物言いに驚く堅太郎にたたみかけるように言葉を次いだ。
「君の性向も政見もよく知っているつもりだ。憲法起草を井上毅と伊東巳代治、そして君とで成し遂げて貰いたい。我が国の近代化は法の整備にかかっている」
ロースクールでの日々がよぎった。さらにたどれば、長薄の命を受けて米国行きの船上で見た伊藤博文のパイプをくゆらす姿、歓迎会での日の丸演説が思い出された。あの時、伊藤博文は言った。
「今の日本はまだ洋上に上ったばかりの太陽で、その光も弱く色も薄い。だが、やがてこの日の丸にデザインされた太陽のように、世界の人々に尊敬の念を持って見られる国となるだろう。そのために、今の日本政府と日本国民が一番望んでいるのは、先進国の最先端の文明を身につけることである…」と。
誇り高く気概をもって日本の近代化を推し進める伊藤博文に、一度は固辞したが自分の場所を見つけたような気がした。太政官権大書記官、ならびに元老院秘書官に任ぜられたのである。堅太郎三十二才の春であった。