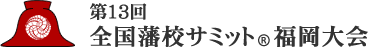次代を拓いた国際人 金子 堅太郎
困難をきわめた影の特命全権大使

ルーズベルトの旧友に対する再会の抱擁は、いくばくかの安心感を堅太郎に与えてくれたが、活動はきわめて厳しいものになることが予想された。堅太郎が到着する二週間前の三月十日、アメリカ大統領令として『局外中立の布告』が出されていたのである。それによればロシア、日本いずれも修交国である。ゆえにどちらか一方に加担する、あるいは応援するというような言論行為は一切厳禁するというものである。いかに親交を温めあった旧知の仲であったとしても一国の大統領が私情から前言を撤回するなどありえない。堅太郎は到着前からすでに困難きわまる交渉が命題となっていたのである。どんな困難も「艱難汝を玉にす」の精神で切り拓いてきた堅太郎だったが、ここへきて窮極の難問が立ちはだかったのだ。
堅太郎がアメリカ入りする頃を見計らって、堅太郎の宿泊先の隣にあるウォルドーフホテルでの一大夜会が開催された。その夜会の入場券の売上金はロシアの赤十字社に寄付し傷病兵の手当てにするという。その席にはロシア大使カシニー伯の宣言書を携えた参事官が招待され、日本を非難しアメリカの同情を惹起するよう巧妙な言辞が披露された。翌日の新聞はその内容が一面を飾っている。これが堅太郎に対する威嚇でなくてなんであろう。
しかもロシアの駐米大使カシニー伯は、ワシントンで連日、記者を優待しハバナの葉巻やシャンペンを飲ませるなどの接待攻勢を行なっては日本攻撃の記事を書かせるのである。さらに今度の戦争は宗教戦争であってキリスト教と非キリスト教の戦いである。欧米のキリスト教国は日本を撲滅しなければならない、などとぶち上げた。新聞記者は新聞記事の切抜きを堅太郎に見せ、「貴下の意見を聞きたい」という。
堅太郎はおもむろに口を開く。
「日本は国際法に違反したことはありません。宗教戦争であるなどもってのほかであります。今日、日本が非キリスト教国であるか、ロシアが非キリスト教国であるかは事実が証明するところです。かつてキリネフでロシア政府が人民の虐殺を行なったことがありますが、これがはたしてキリスト教国のすることでありましょうか。欧米の文明国はすでにご承知おきの事実ではないですか。またロシアは政治犯を極寒のシベリアに送り、甚だ非人道的な扱いをしていることは衆目の一致するところです。日本は憲法をもって宗教の自由を許しています。キリスト教も仏教や神道と同じように保護しています。しかしロシアはどうでしょうか。ギリシャ正教ではカトリックでもプロテスタントでも許さないではありませんか。確かにロシア公使の言うように国土、人口、兵備、どれをとっても日本は劣っています。このことは他国から言われずとも知っています。にも関わらず、なぜこの戦いに踏み切らざるを得なかったか。数年前から日露の関係は悪化し、我一歩譲れば、彼一歩を進み、飽く足らざる圧迫をもって日本に加えています。このまま行けば、日本は遠からずロシアに撲滅される危機に臨んでいましたから、このまま黙ってロシアに滅ぼされるくらいなら、むしろ失敗を度外して進んで剣を取り、国を賭して戦った方が良いというのが、我が日本人の決心なのです。最後の一戦まで最後の一兵卒まで日本は戦います。決して我々は勝つ見込みがあってしたことではありません」
堅太郎のこの談話は翌日の新聞に大きく掲載され、一躍アメリカ人の注意を引いた。事実に基づく理路整然とした堅太郎の弁論は、記者のペンを動かし、アメリカ国民を動かした。
その後、まもなくアイルランドの祭礼でセントパトリック・デーがあり、堅太郎はロシアを頼みとするアイルランド系アメリカ人に宿舎の部屋目がけて脅威行動を起こされるということがあった。ニューヨークの警視総監が訪ねてきたのは度重なる不穏な動きを見るに見かねてのことである。
「ロシアの大使から日本人は暗殺をやりかねないとの訴えがありましたので護衛をつけることにしました。米国は局外中立です。日本に対しても同様に護衛巡査をつけたいのですが、いかがでしょうか」
堅太郎は言下にこれを断わった。
「誠にご厚意は有り難いのですが、私は大使でも公使でもありません。一個人として来ているのですから官府の保護を仰ぐ資格はないでしょう」
「ですが、危険があるかもしれませんから」
「よろしいのです。もし私がロシアの人、あるいはロシアびいきの人から爆弾を投ぜられて死ぬとか暗殺されたならば、金子は満足します。金子堅太郎は命を賭して貴国に来ているのですから、むしろ本望です。金子一人が暗殺されたならば、同情心の強い貴国の一億有余万の方々の半分くらいは同情を寄せてくれるかもしれません。たかが金子一人の死が5千万の米国人の同情に代わるならば私は喜んで死にますから、どうか護衛はお止めください」
堅太郎は再三、脅迫や脅威を受けたが、滞米中ただの一度も護衛をつけることはなかったのであった。ニューヨークを離れ、ワシントンでルーズベルトに会った堅太郎は、先の『局外中立』布告の本当の意味を知る。ルーズベルトは度々堅太郎との会談に時間を割き、堅太郎の危惧を取り払うのである。
「君は局外中立の布告を見ましたか。どう思いましたか」
「失望しました」
「そうでしょう。だから早く君に会いたかった。説明したかった」
ルーズベルトは、日露開戦と同時に自国の陸海軍の若い軍人が日本に勝たせたいとの機運が高まった事実を告げた。そのことにロシア大使が危機感を抱いて抗議してきた結果の布告だという。驚く堅太郎にさらに続けた。
「私、ルーズベルトの腹の中は日本に満腔の同情を寄せています。大統領としてロシア大使の交渉があったからこそ外交上やむを得ず厳正中立を出したまで。私は開戦と同時に参謀本部に命じて日露の陸海軍の軍隊実況を調べました。ロシアの有様、日本の有様はよく承知しています。今度の戦いは日本が勝つ」
「えっ」
予想外の言葉であった。当の日本が、元老の伊藤ばかりか海軍当局、陸軍当局さえ勝ち負けがわからないというのに、縁の遠い米国大統領の言葉である。
「日本は勝ちます。いや、日本に勝たせなければならない。なぜならこれまでの経緯を調べれば、君の論説を聞くまでもなくロシアに非があることは明白である。私はとにかく日本のために働きます。これは君と私の内輪話ですから新聞に公にしてもらっては困ります」
堅太郎は頭上に重くのしかかっていた暗雲が消え去ったような感覚を得るのだった。
「それに君は日本ハーバードクラブの会長ではありませんか。その会長が訪米しているとなったら全米のハーバードクラブ会員が君の味方をするに決まっています」
「そう聞けばなおさら千人力を得た思いです。今の外務大臣小村寿太郎は私と同時に卒業しました。ロシア公使で国交断絶のため引き揚げた栗野慎一郎もハーバード。仁川の海戦で活躍し瓜生外吉は貴国のアナポリス海軍兵学校を卒業しました。つまり四人はみなアメリカの教育を受けています。アメリカで受けた教育を示すのは今であると考えています」
「その決心があればハーバードの連中は間違いなく日本を応援します」
堅太郎はルーズベルトの真意を知るにいたり、ただちに公使館に駆けつけ、暗号電報を小村寿太郎に打電した。伊藤元老はもちろん内閣各大臣がどれほど喜んだかわからない。まさに百万の援軍を得た瞬間であった。
公使に連れられて外務大臣ジョン・ヘイに会ったときも堅太郎は驚かされるのである。紹介状を携えての訪問だが、ヘイは封を開けようともしない。怪訝な表情を浮かべる堅太郎に言った。
「貴下に紹介状は要らないでしょう。私は十四、五年前に貴方に会っているのです」
ジョン・ヘイは議会制度視察で欧米を旅行した際、ワシントンで開かれた晩餐会で会った新聞記者であった。思いがけない再会はまだあった。海軍大臣に面談したときである。
「君は私を忘れましたか」
「存じ上げないと思いますが…」
「ハーバードの法科で同級生でした」
「ビレー・ムーデーという足の悪い人がいたことは覚えています」
「その足の悪いムーデーが私ですよ」
ムーデーはベースボールのチャンピオンで当時、大怪我のため松葉杖をついて通学していた旧友だった。懐かしさがこみあげる。
「今は治ってこのとおりです」
堅太郎は大統領や海軍大臣、外務大臣を旧友に持てた自分の幸福をかみ締めた。どんな困難も心から信頼にたる友人がいれば成し遂げられないことはない。雄弁を弄しても、元老だ、大臣だと威張ったところで三文の値打ちもない。外交はいかに信頼を築き上げられるかだ。それは一朝一夕ではなし得ない。
堅太郎はふたたびニューヨークに戻る。ワシントンでのルーズベルトとの面談やムーデーやヘイとの交流が話題になれば、ロシア大使やフランス大使がまた抗議に押しかけるに違いない。局外中立の立場上、表立って支援・協力は出来ない。まだまだ一人でも多くのアメリカ国民の信任を得なければならないのだ。