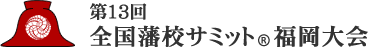次代を拓いた国際人 金子 堅太郎
対話の中の外交の勝利
堅太郎の旧友でスペイン公使を務めていたウードフォードが言った。今は陸軍中将の任にある。
「各界の名士を集めて晩餐会でスピーチをしてみてはいかがだろう。君は私が訪日した際、何かと骨を折ってくれた。あの時の感謝のお返しになるとは思わないが、微力ながらお手伝いしたい。私が主催ということで開きましょう」
「喜んでスピーチさせていただきます」
骨子は日露戦争についてアメリカ人に日本の態度を説明するためである、というものだ。会場はユニバーシティクラブ、開催日は四月十二日と決まった。前内閣大臣、大蔵大臣、陸軍大臣、陸海軍の将校、大審院長、各裁判所の判事、大学総長、外交官、商工会議所会頭、実業家、銀行家、新聞記者他名士二一九人招待された。名立たる招待客のスピーチの後、堅太郎のスピーチがはじまった。日露戦争の原因、状況、日本国民の決心のほどを語った後、堅太郎は深く呼吸し、結んだ。
「二日前、旅順港外においてロシアのマカロフ海軍大将が戦死されました。大将は世界有数の戦術家でありました。我が国はロシアと戦っております。しかし、一個人としては誠にその戦死を悲しんでおります。敵ながらも、マカロフ大将が亡くなったことは非常な痛恨事であると思います。しかし、祖国のために一番に戦死なされたことはロシアの海軍史上、永世不滅の名誉として刻まれることでありましょう。私はここに哀悼の意を表し、大将の霊を慰めたいと存じます」
この日の演説は、翌日大々的に報道され評判となった。それまでロシアのカシニー大使は、日本の悪口を事あるごとに吹聴し、堅太郎にも脅威を加えていたため、その違いが大きく喧伝される結果となったのである。
『日本人は我々欧米人が考えることができない崇高な精神と思想を持ち、それを静かに実践しうる民族である』と新聞で賞賛され、そのことが次から次に講演会の依頼へとつながったのであった。
なかでも大盛況だったのは母校ハーバード大学での講演である。『極東の現状』という演題で数千人の聴衆を前に弁をふるう。時間を超過しても熱心な聴衆にあらためて堅太郎は感謝するのであった。それは武士道の国に生まれ、高い教育を受け、日本の品格を示すことができたことへの感謝でもある。ユニバーシティクラブとハーバード大学二つの講演を通じてアメリカ国民に日本理解が深まり、堅太郎の広報活動は加速した。一年半の滞米期間中、大統領との直接の会見や晩餐会、私邸への招待は二五回、高官・VIPとの会談、晩餐会、午餐会などが六〇回、演説スピーチ一〇〇回以上、新聞への寄稿五回という数字は、おそらく堅太郎以外に成しえない快挙である。
しかし、講演依頼は必ずしも好意的なものばかりではなかった。堅太郎が壇上に立つと演題が違う。司会者が、「お知らせした演題と今日の演題は異なります。突然のことなのでご用意なさったスピーチでもかまいませんよ。日本人のあなたに突然の変更はご無理でしょうから」などと言うこともあった。堅太郎に恥をかかせる嫌がらせなのだが、そんなことで引き下がるような堅太郎ではない。
「わかりました。でも、せっかくなので、どの程度できるかわかりませんが、本日いただいた演題でお話させていただきます」
時にはジョークも交え、にこやかにリズミカルに語る堅太郎にいつしか聴衆は引き寄せられ、予定の時間がきたのでと切り上げようとするともっともっとと言う。最後はスタンディングオベーションの嵐で終了するのである。
「皆様、ご清聴有り難うございました。本日ははからずもほかのお話をさせていただくことができました。ただ、せっかく書いた草稿ですので記念に置いてまいります」
壇上を去った後も拍手は鳴り止まなかったのであった。
スプリングフィールドでの講演会に出かけた時である。留学時代、二週間の夏休みの間、過ごしたホテルのあった地だ。あの時は本当に楽しかった。堅太郎は一瞬、遠い記憶の中にいた。ふとその時である。聴衆の中に堅太郎を見つめる一人の婦人がいることに気づいた。
(あっ)
見覚えのある面影に視線を離せない。キャリイ・アベイ嬢がそこにいたのである。懐かしい日々がよみがえってくる。あのダンス以来、一度も会うこともなく手紙のやり取りさえ満足に出来ず別れた女性だったが、心のどこかに住んでいた。楽屋を訪ねてきたキャリイ・アベイ嬢は、三十数年ぶりに会う堅太郎に古ぼけた博多織の紙入れを見せながら言った。
「あなたはきっと何かを成し遂げられる人だと思っていました」
驚異的な外交戦略、広報活動が功を奏して実にアメリカ国民の八〇%が親日派となった。アンダードッグ観に訴えた戦略を武士道精神をもって体現し、戦争の早期終結に全力で挑戦した結果の勝利である。外交の勝利とは国の誇りを伝え理解させ得ることといえるかもしれない。堅太郎は間違いなく勝利したのである。
明治三十八年(1905年)一月一日、旅順が陥落。ついで三月十日、大激戦の末、奉天を占領し入城。ロシア軍はハルビンに退却する。そして五月二十七日、最強を誇ったバルチック艦隊は全滅する。ここに日本は勝利を得たのであった。自分のことのように欣喜雀躍するルーズベルトが影となりひなたとなって講和の仲介の労を取る。七月になるとポーツマス講和会議のために渡米した外務大臣小村寿太郎の意を受けて連鎖の任にあたる。九月五日、ついにポーツマス条約が調印された。約一八〇万の将兵を動員し死傷者約二十万人。戦費は約二十億円にも達していた。これ以上の戦いは破滅しかない。すでに外債は十三億円も発行されていた。日本軍が連戦連勝してきたのはむしろ奇跡的なことであり、平和を希求する日本政府は賠償金、領土割譲を断念する。だが、世論は厳しく非難が集中するのであった。堅太郎は小村寿太郎の影のように寄り添い言った。
「我々は成すべきことをやりました。日本に平和が戻り戦勝国という誇りを得ました。これ以上何を得ることがありましょう」
その後、十月、小村寿太郎と帰国すると堅太郎は枢密顧問官となり勲一等旭日大綬章を拝受する。枢密顧問官とは天皇の最高諮問機関として重要な国務や皇室の大事に関わる合議機関の一員である。堅太郎は五四才になっていた。
風を見ることはできないが、風の仕業は見ることができる。木々を揺らし波を運ぶ。雲を払い、頬を撫でる。結果が存在を明らかにする。堅太郎は政治家であり外交官として仕事をしただけである。だが、その仕事は誰にもできない不可能を可能にする、困難極まりない課題であり茨の選択であった。その結果があって現在の日本がある。金子堅太郎の風のような陽のような活躍は今も輝きを放っている。
【参考文献】
「金子堅太郎」松村正義「明治三十七年のインテリジェンス外交」
前坂俊之「日露戦争・日米外交秘録」金子堅太郎